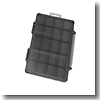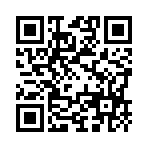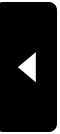2013年07月08日
干潟のカニ
 午前中。 干潮。
午前中。 干潮。実家の前の 遠浅の海。 今となっては とても貴重な 干潟だと思います。

潮が引くと これだけ広大な干潟が顔を出すのは 広島県内でも 珍しいのではないでしょうか。
前日の キス・ギザミ釣り と 島上陸作戦 に出撃した船が しっかり係留されています。
広島市の自宅に帰る前 ちょこっと 干潟を散策し そこで暮らすカニに 注目してみました。
干潟の中にも 砂か 泥など 場所によって 底質が違います

まずは 陸に近い砂浜を 観てみると いたるところに 穴があります

人の気配がすると カニは すぐ隠れてしまいますが じっとしていると また出てきますよ
本来なら スコップで強引に掘って いち早く カニを探し当てたいところですが
時々勢いで カニを傷つけたりすることがあります

ここで オッカム流の カニのとり方を 言わせてください。 キリッ
まず この穴の中に 乾いた白いサラサラの砂を 穴が隠れるまで 入れていきます。
すると カニのすんでいる 少し湿った砂との 色分けがハッキリとできます。
白い砂跡(カニが掘った跡)をたどり 手で ゆっくり掘っていけば 道に迷うことなく
カニさんのところに たどり着きますよ~

砂浜に 穴を掘ってすんでいるから 「スナガニ」 という名称なのかな。
僕らは 「オロオロ」 と呼んでいます。 海で 一番に目にする 慣れ親しんだ カニです。

力が強く はさまれると かなり痛いです 一回はさんだら なかなか はなしてくれません
一回はさんだら なかなか はなしてくれません

逃げ足が 速いです。 ホント すばしっこいんだから・・・逃げたら 捕まえるの 大変です
自分の巣穴じゃなくても 容赦なく 他人のおうちへ 逃げ込みます
砂干潟にも 小さな穴を 見つけることができます。

養分をこし取った砂を だんごのように丸めて 巣穴の周りに ばらまいているカニとは・・・

「コメツキガニ」 でした。 なかなか小さくて かわいいでしょっ

防御?で縮こまってます。 体の裏側は ブルーとピンクが 薄っすらと 煌いています。

干潟には 所々に 水溜り場があり 小さなハゼの仲間も たくさん泳いでいます。

子どもたちは こんなのを 網持って 捕まえたいんじゃないのかな。
同じく 水溜り場で 発見

「マメコブシガニ」 は カニなのに ナント 前に向かって 歩きます。

ごめんね ひっくり返してみると
メス(左)は 卵をかかえるために 折りたたまれた腹部の幅が 広くなっています。

砂にもぐろうとしていた 「キンセンガニ」 を 初めて 見つけました。

砂泥帯には 「オサガニ」 が 巣穴をほって すんでいます。

アマモ場もありました。 水の浄化作用があったり 小魚の隠れ家になったり・・・。

「ハクセンシオマネキ」 の巣一帯です。 スクールが かなり大きな場所でした。

シオマネキングのオス(右)は 片方のはさみが とても大きくなっています。
その大きなはさみを 派手にふりまわす ウェイビングという行動で メス(左)に
求愛するみたいです

シオマネキと同じ場所に まだら模様の 「カクベンケイガニ」 がいました。 名前で 強そう。
ちょっとのつもりが 午前中いっぱいになってしまい 我を忘れ 夢中になってしまいました
子どものように はしゃぎまわり お恥ずかしいです
でも こういう遊びがあるってことを 今の子どもたちに 伝えたいなぁ
最近 埋め立てや 護岸工事により すむ場所が 減っているのが ちょっと気がかりです。
スゴイ!
これだけの海の生き物を探し出す嗅覚と名前が分かるということ!
魚や動物の名前が全く覚えられない(知らない)私にはオッカムさんはネ申です。
そんな・・・ 「ネ申」って言われたら、調子に乗って「カニ(ミ)」だけにダブルピースしてしまうじゃないですか。
この時期、海の生物は、活発に動いています。
「キンセンガニ」と「カクベンケイガニ」の名前は、水の生物図鑑でちょっと調べました。
結構種類がいて、カニがいる場所もちがいます。
カニマップをつくり、干潟にすむカニの分布を調べ、地図に表してみてもおもしろそうです。
ここは尾道です。Tuckerさんも子どもさんをつれて、ぜひ干潟に出撃してください。ハクセンシオマネキは、観てもらいたいです。
満ちてきたら、泳げます。
 at 2013年07月09日 17:21
at 2013年07月09日 17:21カニ博士じゃないですか~
ドクタークラブ?
プロフェッサークラブ?(笑
綺麗な干潟ですねっ
尾道ですか~、とてもよさそうなところですね。
広島の近くにもありますよ、廿日市市の地御前付近です。
時々潮干狩りに行きますよ。
ここのアサリは全く砂を吐かせなくても食べれるのでお勧めです
貝毒が出ていない限り年中食べれますよ。
ただし潮干狩りのさい、路駐にはご注意をっ!!
かなりの頻度で駐禁の取り締まりがあります。
ムフフな駐車場所があるのですが、それは今度お会いしたときに・・・
干潟にはいろんな生物がすんでいることを知ってもらいたく、ついついがんばっちゃいました。(ただ、写真のせただけですが・・・)
潮通りのいいい廿日市の潮干狩りも楽しそうですね、美味しそうですね。
貝以外にも穴ジャコとか、いろいろな発見がありそう。
尾道のここは、漁協の貝の活け場で保全区域となっています。
僕が小学生の時、こんにゃくボールとカラーバットで幼なじみとここで野球していたのが懐かしいです。どんどん潮が満ちてきて大慌て・・・。
 at 2013年07月09日 22:27
at 2013年07月09日 22:27お、おそるべしカニ博士ぶり!
オッカムさん詳し過ぎますけど、
元々そう言った知識をお持ちなんでしょうか?
それだけ物知りでしたら、お子さんたちも楽しいでしょうねー(^^)
私、食べるの専門なもんでして...(^_^;)
子どもの時のカニとり経験が、いかされています。
ただのカニ知ったかぶりです。
干潟ではなく、岩場に潜むカニも紹介したいなぁ。
干潟のどの場所には、どのカニがいるかは、だいたい察しがつきます。
ここでとれる石ガニ(僕らはモガニと呼ぶ)は冬場、身がしまってて、湯がくとおいしく、ビールにあいます。
ゆうにんさん、キャンプの沼にハマるのはいいけど、干潟の沼にはハマらないでね、いにこんでしもうた足が泥から抜けなくなる危険性があります。
 at 2013年07月10日 00:42
at 2013年07月10日 00:42





















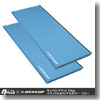














![Coleman(コールマン) 純正LPガス燃料[Tタイプ]【お得な2点セット】](http://img01.naturum.co.jp/goods/09912/771_t.jpg)
![Coleman(コールマン) 純正LPガス燃料[Tタイプ]230g【お得な2点セット】](http://img01.naturum.co.jp/goods/09912/770_t.jpg)



















 スノーピーク(snow peak) パイルドライバー 2014.3.8 5,565円
スノーピーク(snow peak) パイルドライバー 2014.3.8 5,565円